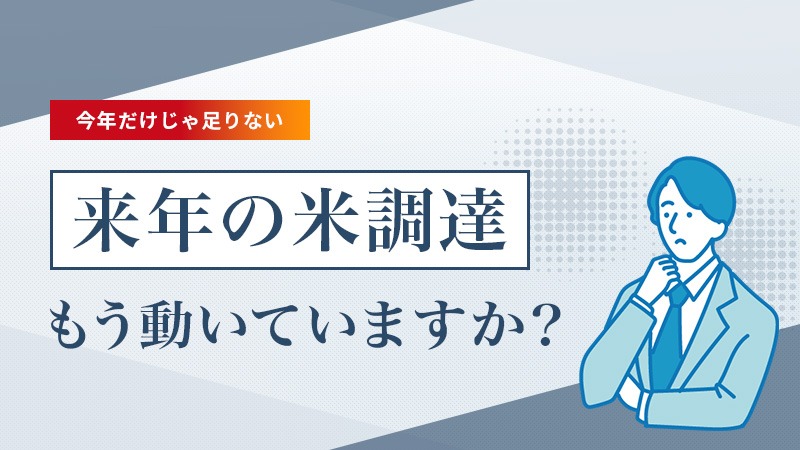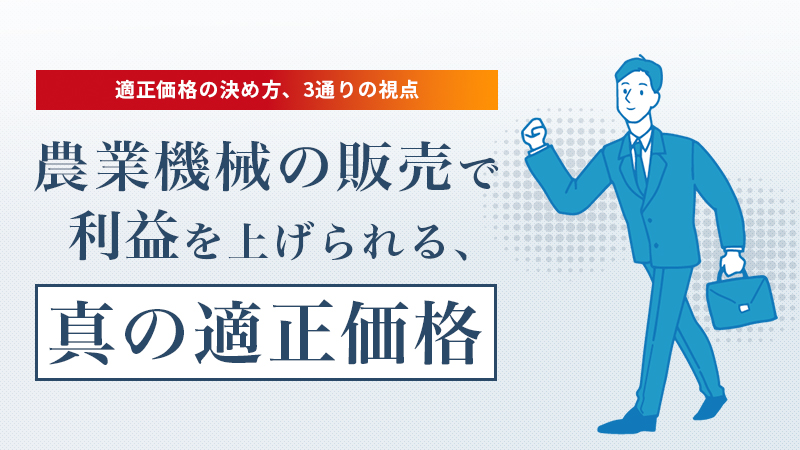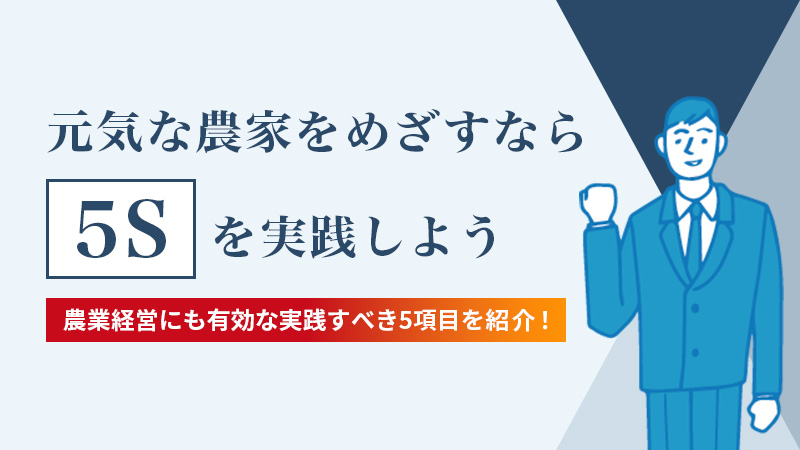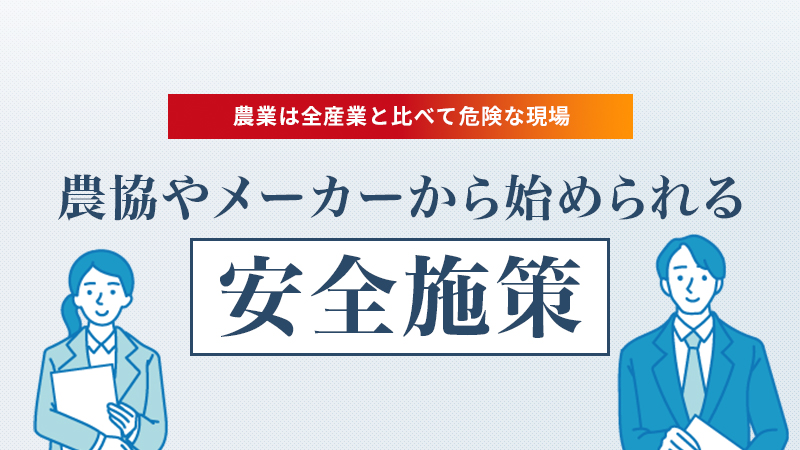農業機械の販売で利益を上げられる、真の適正価格を決めましょう
目次
米の仕入れ現場に今、何が起きているのか
「このままだと、ご飯が出せなくなるかもしれません。」
ある飲食店チェーンの経営者が、そんな不安を口にしました。ここ最近、米の調達をめぐる不安が急速に高まっています。
米価は高騰し、流通も滞り、仕入れの現場では「数量がそろわない」「価格が直前で変わる」などの混乱が起きています。
私たちが支援する飲食店でも、例年どおりの発注をしても、希望通りの米が届かないといった事例が相次いでいます。背景には、需給バランスの崩れと、それにともなう“農家の選別行動”があります。
そして、こうした影響は飲食店だけでなく、農協にも及んでいます。
農協は本来、地域の農家と強いネットワークを持ち、米の流通を支える存在ですが、近年では担当職員の減少や高齢化により、農家とのつながりが徐々に希薄化しています。「調達を頑張っているが、人が足りない」「一軒一軒の農家と向き合う時間が取れない」——こうした現場の声が、静かに、しかし深刻に広がっています。
農家は「高く売れるところ」へ動いている
農家もまた、生き残りをかけた選択を迫られています。燃料や資材費が上昇する中、これまでのように安価で安定的に出荷することが難しくなっています。
そのため、「条件の良い販路を自分で選ぶ」という動きが強まっています。
価格が高ければ売れる、という単純な話ではありません。農家にとって不安なのは、納品後の価格が不透明であることや、あるいは「誰が買ってくれているのかわからない」関係性の薄さなのです。
実際、ある農家はこう話します。
「農協には長年お世話になってきたけれど、最近は誰が担当なのかわからない。直接話す機会も減ったし、ちょっとした相談も難しくなっている」
その一方で、「この米は本当に美味しいと焼肉店のお客さんが言っていたよ」と伝えてくれる飲食店との取引には、喜んで応じていました。農家にとって、「価値をわかってくれる相手」との関係は、価格とおなじくらい重要なのです。
調達は“命令”ではなく“戦略”で動かす時代へ
飲食店や農協の多くが、毎年の米の確保に奔走しています。発注量の指示、人員の配置、予算の割り当て——どれも現場の必死の努力の賜物です。
ただし、それだけでは時代の変化に対応できなくなってきています。農家側の状況も、流通の構造も変わってきている今、本当に必要なのは「来年をどう確保するか」という中長期的な戦略です。
年間100トンの米を調達するには、およそ20ヘクタールの水田が必要です。1,000トンであれば、200ヘクタール。こうしたボリュームを安定的に確保するには、単年契約では限界があります。
いま必要なのは、「どう確保するか」ではなく、「誰と関係を築くか」。この視点をもった取り組みが、調達の未来を支えます。
農家との“間”が空いてしまっている
農協の現場でも、職員一人あたりが担当する農家数が増え、一軒一軒と深く対話することが難しくなっています。営農指導や集荷、配送などの業務に追われる中、「最近どんな栽培をしているのか」「何に困っているのか」といった個別の声を拾う余裕がありません。
こうした状況下で農家との“間”ができてしまい、「売っても反応がない」「誰に届けているのかもわからない」といった不満や孤立感が募っているのが実情です。
その一方で、飲食店チェーンなどが農家に直接声をかけ、「うちで使わせてください」と訪ねるケースが増えています。我々もお米調達のため初めて会う農家さんから「会いに来てくれた」「どんな工夫をしているのか聞いてくれた」というだけで、農家は心を開き始めます。
つながりの希薄化は、放置すれば確実に“離反”へつながります。農協が本来持っていたネットワークの強みを、もう一度取り戻すには、調達そのものの考え方を見直す必要があるのです。
サプライチェーンと関係構築の両輪が必要
私たちは現在、飲食店や農協に代わって農家との橋渡し役を担う中で、調達には「物流」だけでなく「関係づくり」が欠かせないと実感しています。
農家との契約、栽培調整、乾燥・調製・保管・精米・配送まで、全体を見通したサプライチェーンの構築はもちろん大切です。
しかしそれ以上に、「誰と、どんな関係を築くか」という人間的な視点がなければ、良い流通網も機能しません。
ある農家が言っていました。「今年も来てくれるかなって思ってたけど、連絡がなかった。そしたら他から声がかかって、そっちと決めちゃった」
農家は、買い手の姿勢を見ています。未来を見据え、言葉を交わし、共に“食”をつくる意識を持った相手でなければ、継続的に付き合おうとは思ってくれません。
最後に:農家との信頼を、いま再構築するために
米の調達は、いま転換点を迎えています。安さだけでは選ばれず、命令だけでは動かず、信頼がなければ確保できない時代に入りました。
農協の皆さまも、飲食店の皆さまも、目の前の業務に全力を尽くしていることは重々承知しています。しかし、それでも農家との間に“すきま”が生じている現状を見過ごしてはいけません。
私たちは、農家との信頼関係を築き直すための調達代行や連携支援を行っています。農家と飲食店・農協の“あいだ”に立ち、双方の言葉と想いをつなぐことで、安定した未来の供給体制をつくりたいと考えています。
「今年の米」だけでなく、「来年の米」を確保するために。
そして、その先の未来に向けて。いまこそ、“人とのつながり”を再構築する一歩を踏み出しましょう。
次の世代のために一歩前へ進みましょう。
皆様からのご連絡をお待ちしています