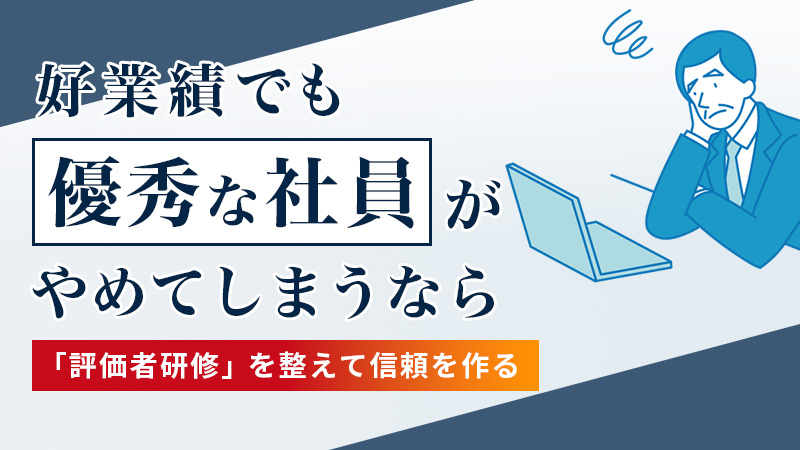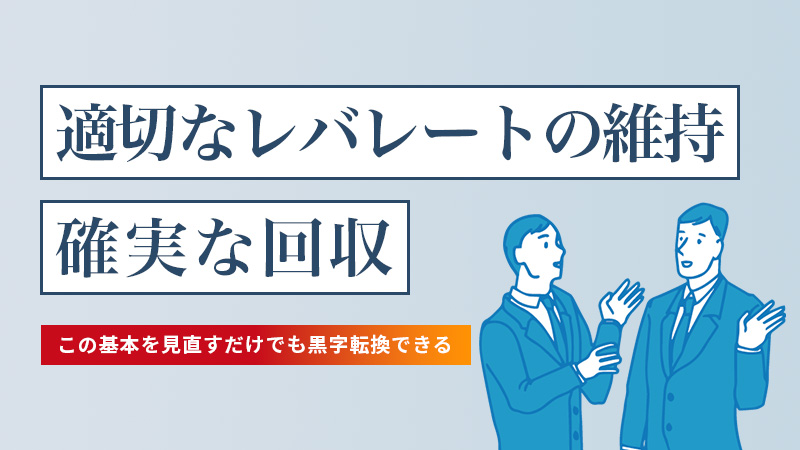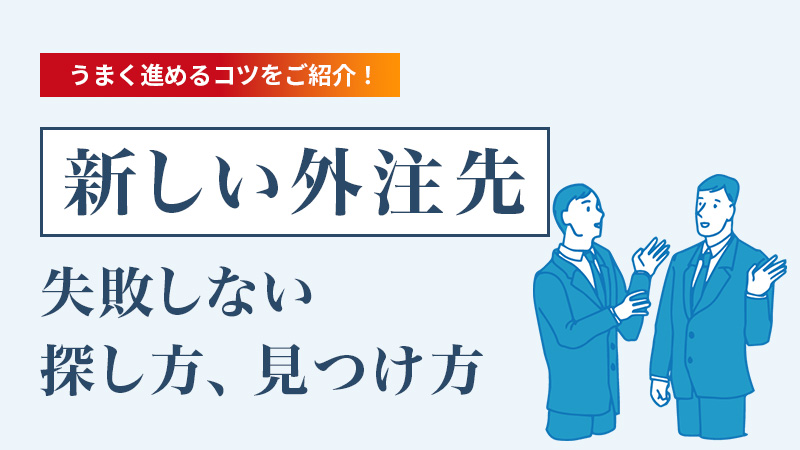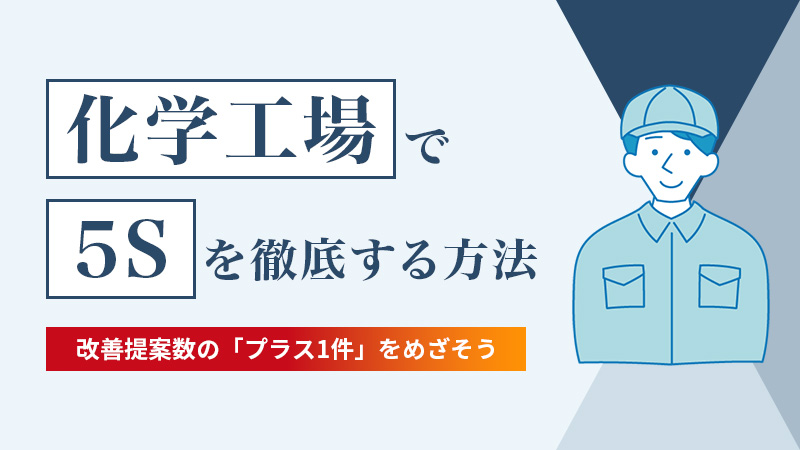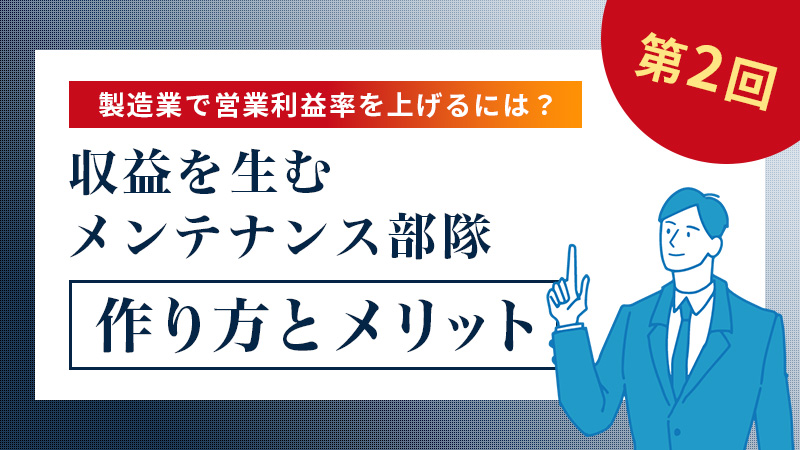適切なレバレートの維持と確実な回収 この基本を見直すだけでも黒字転換できる
せっかく業績が上がったのにリーダーが育たない、優秀な人材が辞めてしまうと感じるのであれば、「評価者研修」を見直してみましょう。「評価者研修」を継続的に行っている企業は少なく、1回開催だけで終わってしまうケースも見られます。
若い世代は人事評価の基準を明確にしないと納得しません。仕事における評価に波があると、優秀な社員ほど会社に不信感を持って離れてしまいます。会社としての軸を明示し、離職を予防できるのが定期的な「評価者研修」なのです。
実際に公平な評価を行うには、管理者側が共通の物差しを持つ必要があります。その基準を会社としてすり合わせて整えるのが「評価者研修」の役割です。
評価者研修の進め方
抽象的な概念を評価するのは難しいものです。例えば細かい指摘をする部下がいた場合、一方では協調性がないとされるかもしれませんが、裏返せば合意形成に対する気配りとして評価できます。このようなケースをどう判断するか企業によって違います。
私たちが提供している研修では、事前にヒアリングを行って研修企業に即したサンプル事例を示します。このサンプル事例に対して参加者がそれぞれ5段階評価を行い、お互いの理由を述べた後に共通の基準を作っていきます。
このほか、リーダーシップ/主体性/創造性/技術力などさまざまな評価項目についても管理者全員で基準を統一し、部下に向けて「今の物差しはこうなりました」と明示してもらうまでがカリキュラムです。
管理者に評価視点ができる
「評価者研修」を行うと、管理者が「どこを見て評価すべきか」を把握できるようになるのもメリットです。日常業務での観察力が高まり、部下にとっては「しっかり見てもらえている」「正しく評価されている」という実感につながります。その実感は優秀な人材がさらに努力する基盤となります。
また、1on1の面談でも「あのときの発言」や「具体的な実践」といったエピソードを根拠に評価でき、説得力あるフィードバックが可能になります。
上層の幹部たちが気を配るべきこと
ただ、評価する管理者自身が基準より「甘くしよう/厳しくしよう」と個人的に調整してしまう傾向は避けられません。これは上層の役員が最終確認する際に中立性を意識し、全体の評価を調整することで対応するのがよいでしょう。
管理者それぞれの傾向を把握するためにも、「評価者研修」は管理者を一堂に集めて行うことが重要です。少なくとも年に1回は実施するのを推奨しています。
年に1回以上行うのは、会社方針や評価すべき行動などの条件が年々変化するからです。これを怠ると方針から外れた評価が行われたり、本来貢献している社員の評価が低くなったりして不信感や離職につながってしまいます。
第三者をうまく使って「評価者研修」を開催する
業績が上がっているのに人材が流出してしまうとすれば、それは評価の仕組みがうまく機能していない証拠です。
それに気づいた人事担当者の多くは、人材定着のために制度を見直し、評価軸を整備したいと考えています。もし忙しい管理者を集めて「評価者研修」を実施するのが困難であれば、そのときは中小企業診断士など第三者の力を使ってください。私たちには開催につなげるためのノウハウがあるからです。
私たちが管理者の皆さんを説得するときは「現場で人材が不足していると感じるなら、まず社員の皆さんが意欲的に働ける環境を整えるべきです。そのためには適切な評価とフィードバックが欠かせません。
その理想を実現する第一歩として、属人的ではない客観的な評価基準を、みんなで決める研修が必要なのです」と話しています。
第三者が入ると「評価項目が多すぎて管理者の負担が大きかった」「評価基準が方針と合っていなかった」といった課題が客観的に見えてきます。社内では言いにくい生の声も聞こえてきます。
「評価者研修」はしっかりした「評価の物差し」を作るだけでなく、人事制度運用の問題点も明らかにする良い機会となります。「評価者研修」のカリキュラム作成や伝え方についてもアドバイスができますので、一度ご相談いただければと思います。
次の世代のために一歩前へ進みましょう。
皆様からのご連絡をお待ちしています