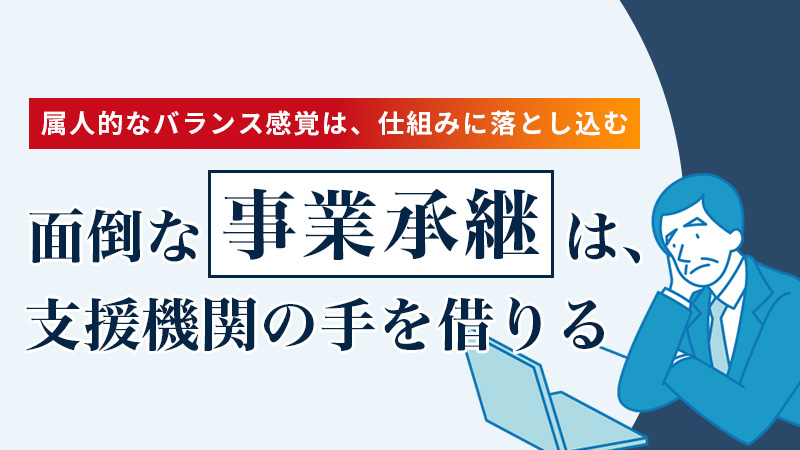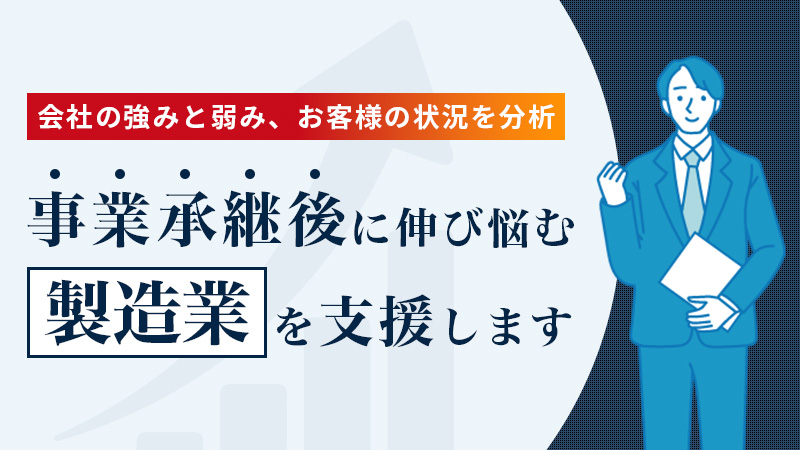事業承継後に伸び悩む製造業を支援します
黒字のまま廃業してしまう企業が東京だけでなく全国で増えています。
統計では廃業する企業の約6割が黒字といわれ、正直、これは非常に勿体ないと感じています。長年継続してきた企業にはお客様の信頼と社会に役立つ事業があるにもかかわらず、廃業によってその存在が途絶えてしまうからです。
皆さんが廃業に至る背景には、「自分の会社は自分にしか経営できない」「手続が面倒」という思いがあるようです。しかし事業承継を諦めて廃業・清算を選んだとしても、多くのコストと手間が伴います。
まず廃業を進める期間は収入が激減しますが、在庫処分費や事務所維持費・人件費は同様にかかります。無収入で固定費がかかる期間が発生します。弁護士など専門家への依頼費用も必要です。
そのデメリットを考えると、廃業を選ぶより事業承継するほうが心理面でも金銭面でも「楽だった」と感じるケースが少なくないのです。
目次
事業承継のメリット
何よりもお客様の信頼を資産として残せるのが大きなメリットです。
いままで事業を続けられてきたということは、お客様のニーズをつかんで応え続けてきたということ。いままで指示してくださったお客様の信頼を裏切らずに残せます。
また、戦略次第で事業承継は個人の収入づくりにもつながります。
例えば、ある機械販売業では顧客・商圏・建物などをメーカーに売却する一方、土地は元経営者所有のままとし、10年間は移転しないという条件で賃貸契約を結びました。これにより売却益とともに安定的な家賃収入が得られています。
役職を社長から会長へと移す形式なら、会社に居場所を残すこともできます。
他社へ売却する場合でもアドバイザー契約を結べば、収入を得ながら、育て上げた会社と正式な形で関わり続けることも可能です。これらは東京など都市圏だけでなく地方でも用いることのできるテクニックです。
事業承継前のチェックポイント4つ
事業承継を成功させるには「経営者のバランス感覚を仕組みに落とし込む」ことが重要です。実践ポイントは4つあります。
① 財務を透明化する
何がどれだけあるかという在庫管理、何がどれだけ売れたかという売上、どのくらい費用がかかったかという原価構造を見直します。創業や引継の当初から比べればかなり状況が変わっているはずです。
② 顧客情報の整備
どんなお客様が、いつ、何を購入しているのか。それは誰が担当しているのか。情報をリストにして整頓しておきます。
上記①②を見直せば、利益率が低い不採算部門が明確になります。その場合、承継時に「これをやめよう」という選択も可能です。不採算部門をなくすための投資であれば、銀行も融資しやすいでしょう。
③ 従業員の安心を得る
従業員の不安を解消する中長期的な計画も必要です。例えば、営業や技術で顧客と密接に関わっているキーパーソンが辞めてしまうと、会社の信用自体が揺らいでしまうこともあります。
彼らに安心してもらえるよう、承継後はどんな経営方針でいくか、新たに何をめざすのかを伝えるのが大切です。短期で説得するより、中長期における①②の実践を見てもらうのが最善です。
④ 法人財務と個人の経理を分離しておく
経営者によっては個人の支出と会社の支出が混在している場合があります。これは承継前に帳簿としてしっかり分離しておきます。承継時には金融機関から必ず「過去3年の財務諸表を見せてほしい」と依頼が来るからです。
上記①〜④の準備を考えると、承継に関する準備期間は3年以上、少なくとも5年前から始めるのが理想的です。
事業承継の面倒な部分は外注していい
承継の過程で最も大変なのが、家族・従業員・金融機関への説明です。これを経営者一人で行おうとすると負担が大きく、面倒に感じてしまうこともあるでしょう。
実はこの「最も面倒なところ」が「最も支援機関に任せてよいところ」です。すべてを自分で抱え込まず、頼れるところは頼ることが事業承継をスムーズに進めるコツです。
専門家の知見を使えば、有利な税制や補助金を使って承継する、円滑な相続にもつなぐ、より良いマッチングを実現する、そんな事業承継も視野に入れられます。
皆さんが築き上げた事業と資産を良い形でつないでいくためにも、疑問や悩みがありましたらぜひ私たちにご相談ください。
次の世代のために一歩前へ進みましょう。
皆様からのご連絡をお待ちしています